作業療法士(OT)として働きながら、「もっと知識を深めたい」「他のOTと差をつけたい」と感じていませんか?
臨床現場では、国家試験に合格しただけの知識では通用しないことも多く、勉強を継続することが非常に重要です。
この記事では、「現役OTが実践している“本当に効果のある勉強法7選”」を紹介します。
新卒OTはもちろん、中堅OTや復職を考えている方にも役立つ内容になっています。
ぜひ、最後まで見てくださいね!
1. なぜ作業療法士に継続的な勉強が必要なのか
医療現場は日進月歩。日々アップデートされています。
ガイドラインの改訂や評価法の見直し、疾患ごとの治療戦略など、最新の情報を知らずに臨床に出ることは、患者さんの不利益にもつながりかねません。
また、作業療法は患者さんや他の医療従事者にわかってもらいにくいことも多く、説明力=知識量が評価に直結する場面も多くあります。
2. 勉強を継続できるOTの共通点
継続的に学び、現場で信頼されているOTには共通点があります。
- スキマ時間をうまく活用している
- 興味のある分野から学び始めている
- 目標(キャリア、資格、職域)を持っている
- アウトプットを多くしている(指導、交流、SNS、ブログなど)
「やらされる勉強」ではなく、「主体的に学ぶ」ことが継続のコツです。
3. 作業療法士におすすめの勉強法7選
① 専門書・教科書の読み直し(基礎の再確認)
新人〜中堅OTに特におすすめ。
「脳卒中の作業療法」「高次脳機能障害の理解と作業療法」などの定番本を、現場の事例と照らし合わせながら再読すると、理解が深まります。
📚おすすめ書籍の選び方
・疾患×基礎×評価
急性期、整形外科なら(リスク管理・整形外科学・評価学・機能解剖)
現場に出ると、作業療法の知識にとどまらず、疾患や治療の知識も充実させたいところ。治療方法からリハビリテーションを考えられるようになると理解がさらに深まります。
② 学会・研修会・WEBセミナーへの参加
最近はオンラインセミナーが主流になり、地方在住でも質の高い学びが得られます。
💡ポイント:
・日本作業療法士協会、各都道府県OT協会主催のセミナー・民間団体のセミナー
所属している病院や施設によっては、研修会費を出してくれるところもあります。積極的に活用していきましょう。どんな研修会がいいかは先輩に聞くのがおすすめ。
③ スマホアプリやYouTubeの活用(スキマ時間に最適)
例えばYouTubeで「高次脳機能障害 作業療法」「作業療法 アプローチ」などを検索すると、臨床に直結する知識が無料で学べます。
⚠️YouTubeやSNSを活用するときの注意点
知識の正確性、信頼性を判断する。間違った知識を発信している人もいるので最終的には自分で調べて取捨選択できる力が必要。
④ 症例検討・ケーススタディの共有
勉強会や職場内ミーティングでの症例検討は、実践力を高める最高の勉強法です。
「自分ならどう介入するか?」を常に意識して考えることで、知識の定着にもつながります。
💡ポイント
自分の症例検討の場合:はじめに何に困っているか、何について検討したいかを明らかにする
他の人の症例検討の場合:とにかくひとつは質問、意見を述べる。
⑤ SNS・ブログでの情報発信(アウトプット)
InstagramやX(旧Twitter)、note、ブログなどでアウトプットすることで、知識が自分のものになります。
同じOTとの交流にもなり、学びのモチベーションが上がります。
💡ポイント
とにかくアウトプットすることで知識は定着します。同僚や先輩、後輩に話をしてもいいですが、いつでもどこでも自分のペースでできる情報発信がおすすめです。私もこのブログで情報発信をしていますが、Instagramで画像をまとめて発信すればスライド能力も高くなるし、伝える技術が格段に向上します。公開アカウントが恥ずかしければ、非公開アカウントでもかまいません。
⑥ 資格取得を目指した勉強
将来的に以下のような資格を目指すことで、モチベーションを保ちつつ体系的に学べます。
- 認定作業療法士
- 福祉住環境コーディネーター
- 認知症ケア専門士
- 介護支援専門員(ケアマネ)
資格があることで給与に反映してくれる施設もあるのでキャリアアップとしてもおすすめです。
⑦ 英語論文・最新ガイドラインを読む
敷居は高いですが、PubMedや国際的な作業療法誌を読むことで、最先端の知識を得られます。
翻訳アプリやAIを活用すれば、意外とハードルは高くありません。
4. 勉強を習慣化するためのコツ
- 毎日15分だけ勉強する
- カレンダーに「勉強予定」を入れる
- 仲間と「勉強報告」をし合う(SNSやLINEグループ活用)
- 勉強したらSNSにアウトプットする
5. まとめ:勉強が“差”を生むOTになる第一歩
作業療法士にとって、知識と実践力は“信頼”を築く武器です。
学びを継続することで、患者さんとの信頼関係が深まり、職場でも「頼られるOT」になれるでしょう。
✅ 具体的なアクションプラン
- 教科書、参考書を1冊読む
- 気になるセミナーに参加する
- SNSで発信している人を探す
- 勉強内容を発信する(SNS、YouTube、ブログ、なんでもOK)
- 1日15分でいいから1ヶ月間継続する
「知っている」だけではなく、「現場で使える知識」に変えていきましょう!





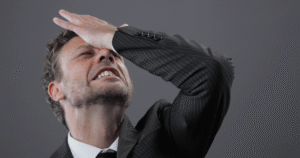



コメント